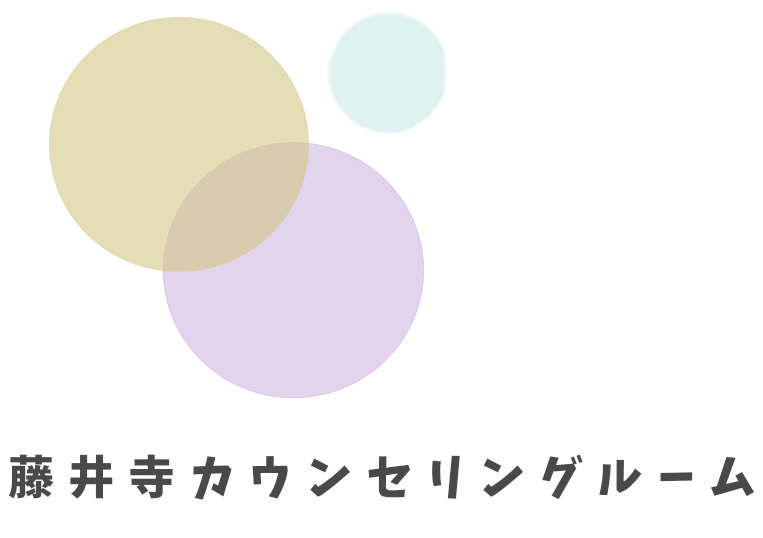「臨床の基盤となる「視点」を得るための研修会」ですが、おかげさまで参加者が集まってきております。
先日のお知らせにも記載しましたが、アーカイブ配信が決定しました。
当初のしめきりギリギリでの決定となってしまいました。申し訳ありません。
つきましては、研修参加のしめきりを、5/22(日)まで延長させて頂いています。
本研修会が、心理業界において、何か大きなうねりになることはないと思いますが、講義や「ゆるやかな横のつながり」を通して、静かに自身の臨床をみつめる/かたちづくるものになればよいなと考えております。
まだ参加枠に空きがありますので、ぜひ参加の方ご検討ください。
失礼致します。
投稿者: cocuri
視点研修 アーカイブが決まりました
視点研修をアーカイブ配信をすることが決定致しました。
研修開催時から、準備しお知らせすべきことでした。失礼致しました。
当初予定していた、締め切りの1日前のアーカイブ配信決定の通知となってしまいました。申し訳ありません。
つきましては、締切を5/22(日)まで延長させて頂きます。
アーカイブも含め、参加のご検討のほど、よろしくお願い致します。
アーカイブに関して、いくつか注意点がございますので、ご一読ください。
①11/6(日)の、永野浩二先生の「当事者研究とオープンダイアローグ」のみ、講師の意向のもと、アーカイブ配信は実施しません。
事務局の解釈ではありますが、「当事者研究やオープンダイアローグ」は、アーカイブではそれらの核の部分が伝えられないと考えられます。
ぜひ、永野先生に、アーカイブではなぜ学びきれないのか、という質問をぶつけてみたいと考えています。それにより、「当事者研究」「オープンダイアローグ」の真髄と、ひいては臨床的に大切なこととは何か、触れられるのではないかと、今から楽しみです。
②アーカイブ配信はあくまで、どうしても参加できなかった時のためのものとして頂ければ、事務局としてはありがたいです。
本研修は「少人数制で、それぞれの思いや考えを講師に発信し、対話を通じて視点を得ていく」ことに特性があると考えます。
受講者それぞれの臨床観や臨床フィールドと「理論・学派・オリエンテーション」がどうマッチするのか(もしくはしないのか)は、対話を通すことで、より体感的に理解できるでしょう。
みなさまの積極的な対話で、全体にとっても実りのある研修になると考えられます。よろしくお願いします。
③アーカイブ配信は、講義終了後2週間とさせて頂きます。詳細は準備でき次第、受講者にお知らせさせて頂きます。
以上です。
よろしくお願い致します。
事務局の思う、視点研修の魅力
アーカイブ配信が、確定しきれず、申し訳ありません。
もう少々だけお待ちください。
それにともない、締切日はのばす予定をさせて頂いています。
少々お恥ずかしいですが、事務局が思う「臨床の基盤となる「視点」を得るための研修会」の魅力をお伝えさせて頂きます。
あくまで事務局の考えであって、各講師の先生方が下記の思いに同意されるか否かは分かりませんが。
当研修は、各理論、視点、オリエンテーションの概要を知るだけでなく「どのような人がどのような思いで」という側面を重視しています。
それらを知るためには、講師の先生の人柄に触れられることや、先生との対話も重要であると考えるので、少人数での実施を予定しています。
そういう思いがあったので、当初の想定では、オンラインではなく対面での集合形式を検討していました。
ただやはりコロナ禍ということもあり、また関西以外の方の参加も見込み、オンラインでの実施に至りました。
オンラインだからこそできる対話の形式をもてるようにします。
著名な先生方が講師として参加してくださいますので、さまざまな場で、ご講義を聞いたことはあるかもしれませんが、自身の思いをぶつけられる機会は貴重ではないかと思います。
その対話を通して、自身にマッチする理論、視点、オリエンテーションを体感してもらえたらうれしく思います。
自身の関心のあるものを詳しく、包括的に知るための研修にもなると思いますし、何かのオリエンテーションに定めることに一歩踏み出せなかった方は、その一歩を踏み出すきっかけになるかと思います。
また現在関心がないものの講義も、それらを知ることで臨床上の共通点などを知ることができ、幅の広い視点をもてるのではいかと考えています。
蛇足になりますが、最後に少しだけ。
さまざまなご意見や制度設計の問題などはあるでしょうが、これからはゆっくりと、着実に公認心理師資格が重要になってくる時代になるだろうと想像します(だからこそスキマ世代問題は解決して欲しいのですが)。
公認心理師資格に、講義で扱うような理論、オリエンテーションのエッセンスをしっかり根付かせることが、臨床心理士として活動してきたものの責務かと感じたりしています。
ぜひ、ご参加の方をご検討ください。
参加予定の方は一緒に豊かな学びができることを楽しみにしています。
失礼します。
「問い合わせ」から送信して頂いても、事務局に届いていない事案が出ています。
もし該当の方がおられましたら、お手数おかけしますが、再度「問い合わせ」から送信頂くか、072-959-6515(月~金曜の9:00~17:00)のいずれかにご連絡ください。
また、アーカイブ配信に関しては、現在調整中です。
もう少々お待ちください。
なお、アーカイブのことが明確になってから、再度申し込みをご検討頂ける方もおられると思います。
つきましては、申し込み締め切りは、4/30(土)から延期する予定です。
こちらも、正式に決定でき次第、ここでお知らせ致します。
よろしくお願い致します。
視点研修 アーカイブ
臨床の基盤を得るための「視点」を得るための研修会ですが、参加者募集中です。
講義で扱う、学派/理論/オリエンテーションの違いと共通点を知ることで、臨床における肝のようなものを学んで頂けるのではと思います。
ぜひ、ご検討ください。
また、アーカイブはないのか、というお声を頂いています。
何かしらのかたちでアーカイブは残そうと調整中です。もう少々お待ちください。
正式に決定し次第、ここのHPにてお知らせさていただきます。
なお、それにつきまして、しめきりも再調整が必要かもしれないと考えています。
初めての研修運営で、ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。
研修情報 視点研修①
初めまして。
まだ、未開設ではありますが、約1年後をめどに、藤井寺カウンセリングルームの解説を目指しております、NPO法人こくりの大原といいます。
研修事業は、2022年度より順次開催していきます。
その第1弾は「臨床の基盤となる「視点」を得るための研修会」 通称「視点研修」です。
詳細は「研修情報」をご参照ください。
一応、定員を設けておりますので、定員の状況などを、随時お知らせしていきます。
この2月より、フライヤーを配布させて頂いており、現状空きは十分です。
では、今後ともよろしくお願い致します。